こんにちは!ペンデル税理士法人 医業経営支援部 親泊です。
今回は、クリニックの事業承継においてとても重要な「患者さんの引継ぎ」について、詳しくお話しします。
財務や経費、資産の確認ももちろん大事ですが、
それ以上に「どんな患者さんが来院しているか」「普段どんな診察をしているか」など、
クリニックの運営に密接に関わることも重要です。
新しい院長の紹介や患者さんの対応方法なども、事業承継の中でしっかり確認していきましょう。
(コラムの内容は公開時の法律等に基づいて作成しています)
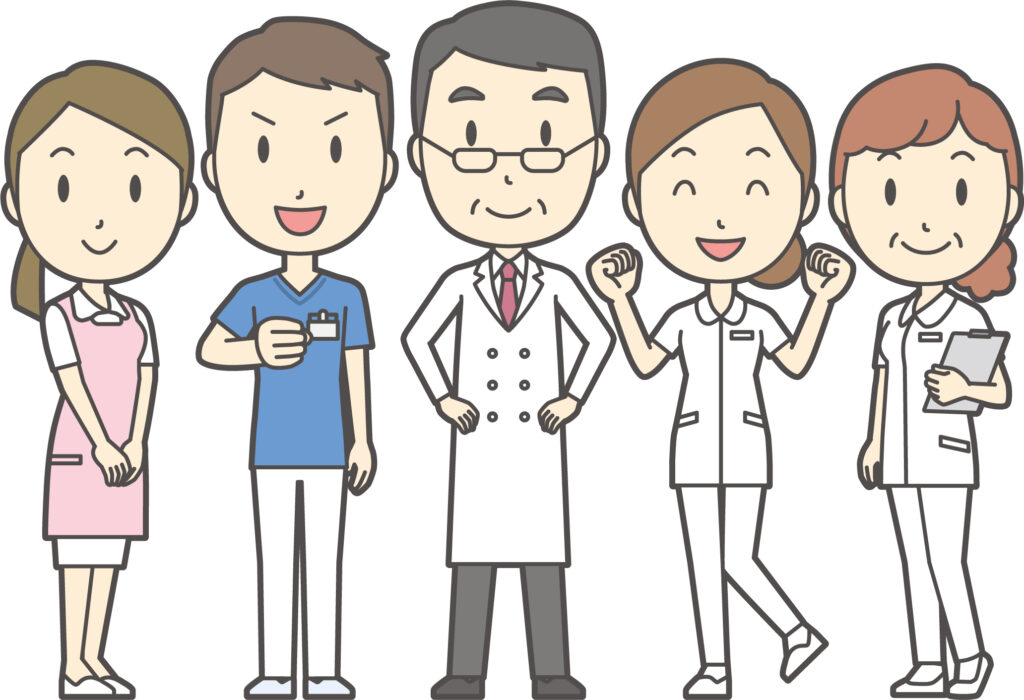
まず、引継ぎにおける「制度上」の必要性について
原則として、保険診療を行うには、診療開始の前月の締切日までに
地方厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出し、審査を経て指定を受ける必要があります。
この申請は、診療所を個人から法人に移行する場合や、
診療所の移転、保険診療の新規開始などの場合に必要です。
例えば、4月1日から保険診療を始める場合、申請は3月初旬に提出しなければならず、
申請から指定されるまで約1か月の「空白期間」が生じます。
この間に診療を続ける場合、特例として指定日を遡ることが認められるケースもありますが、
そのためには「患者さんのしっかりとした引継ぎ」が条件となります。
実務上の引継ぎ
実務的な引継ぎとしておすすめなのは、まず引継ぎ契約を締結し、
その後、新院長が非常勤や常勤としてクリニックで実際に働きながら、
患者さん対応やスタッフの仕事内容を確認することです。
前院長が診療している際に陪席し、新院長として患者さんに紹介してもらうことも効果的です。
この期間は、患者さんへの案内が進むため、できるだけ長めに設定した方がスムーズに進みます。
もし新院長が頻繁に勤務できない場合は、カルテ上で患者さんごとの注意点を確認し、
職員の業務内容も把握する方法なども検討してください。
必要な届出は?
個人診療所の場合、
新しい勤務医が入職する際には、保健所と地方厚生局への変更届提出が必要です。
保健所への届出は勤務開始後10日以内ですが、
場所によっては医師免許の原本確認が必要なので、事前に確認しておきましょう。
地方厚生局への届出は、保健所への変更届の後に行います。
医療法人の場合、開業エリアによってルールが異なることがありますが、
基本的には地方厚生局への届出のみでOKです。
給料はどうする?
引継ぎ前に勤務を始める場合、給料の設定に悩むかもしれません。
ケースバイケースですが、いくつかの事例を紹介します。
診療を伴わない陪席のみの場合
前院長から新院長への患者さん引継ぎのための陪席と考え、給与を発生させないケースです。
比較的、陪席日数が少ない場合が多く、2,3回で終了することもあります。
買い手側が電子カルテの操作に慣れていたり、
院内の医療機器が少ない診療科目などで多い傾向があります。
勤務医扱いで給与を支給する場合
比較的長期間もしくは複数回、勤務される場合、勤務医として給与を支払うケースです。
金額設定は、多少安め~地域相場で設定することが多いでしょうか。
契約締結から引継ぎ日まである程度期間がある場合や、2診体制が可能な院内設備で、
新たに医療機器を入れて習熟が必要な場合などで多い傾向があります。
カルテ上で、前院長からレクチャーを受ける場合
少しイレギュラーですが、陪席や通常の勤務内で患者さんの引継ぎが終わらない場合に、
前院長から別途引継ぎのレクチャーを受ける場合があります。
この場合、上記とは逆に、買い手側がレクチャー費用をお支払いされるケースもあります。
引継ぐ診療所の運営方法に特色がある場合や、どうしても買い手の時間が取れない場合に
お願いすることがあります。
いずれの場合でも、後でトラブルにならないよう、しっかりとした引継ぎを行うことが大切です。
まとめ
事業承継を円滑に進めるために、単にお金の話だけではなく、
「どうすれば患者さんがこれまで通り来院してくれるか」をしっかり考えることが大切です。
これまで長期間診療されてきた前院長と、患者さん対応や診療方法が変わるのであれば、
より丁寧な引継ぎが本当に重要ですので、
患者さんが安心して、次の院長でも受診できるようにすることが、成功の鍵です。
もし、引継ぎ方法でお困りであれば専門家のサポートを受けるのも一つの手です。
ペンデル税理士法人 医業経営支援部では、
クリニックの事業承継に関するサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、問い合わせフォームからどうぞ。

しっかりとした、患者さん引継ぎ。
地方厚生局によっては、引継ぎに対する基準が異なることがあります。
親子間の承継ではない第3者承継の場合、常勤での勤務が必要だったり、
非常勤の場合でも最低2か月の勤務が求められることがあります。
しっかりとした引継ぎが認められないと、
保険診療開始までに1か月の待機期間が発生することもあるため、
申請や届出は人任せにせず、自分でも確認するようにしましょう。
